
 |
ウィンザー・マッケイ
|
| 時代を超えて愛され、今なおファンを増やし続けているアメリカ新聞マンガ史上最大の傑作のひとつ、それがウィンザー・マッケイの『眠りの国のリトル・ニモ』だ。 ニモ少年と仲間たちが夢の世界で奇想天外な冒険を繰り広げては、最後に窮地に陥ったニモ少年が夢から醒める、というのが毎回踏襲されるパターンだが、その夢は、眠りの国の王女さまからお招きを受けたり、巨大化して夜の街をさまよったり、と子供らしく無邪気なときもあれば、ときに大きな七面鳥に家ごと持ち上げられたり、火星で火星人の空賊(?)にさらわれたりと、危険や恐怖に満ちていたりもする。精神分析を知る人間なら、作者のマッケイが夢のメカニズムを熟知していることに驚嘆するに違いない。 新聞の日曜版一面分をまるごと費し、正確なデッサン力と流麗なタッチ、そして溢れる想像力をもって描き出された夢の世界のようすはまさに芸術的というほかなく、スラップスティックが全盛だった当時の新聞マンガの中では異彩を放つと同時に、コミックスのもつ表現の可能性を大きく広げることとなった。その影響は現在に至るも続き、メビウス |
やビル・ワターソン、クリス・ウェアなど、ウィンザー・マッケイにオマージュを捧げるマンガ家はいまだに跡を絶たないばかりか、『コミックス・ジャーナル』誌は『20世紀のベスト・コミックス100』の第5位に『ニモ』を選出している。なお、マッケイはアニメーション映画の創始者のひとりとしても知られており、自らペンをふるってアニメ化した『恐竜ガーティ』や『ニモ』は初期アニメーションの古典と位置づけられている。 『ニモ』は1905年10月15日から1911年4月23日まで『ニューヨーク・ヘラルド』紙に、タイトルを『素晴らしき夢の世界で In the Land of Wonderful Dreams』と変更して掲載された。 本書は『ニューヨーク・ヘラルド』時代の作品を抜粋し、デジタル処理により色や裏映りを補正した上で、当時の新聞の原寸大で再現したもので、マッケイの意図にもっとも近づいた版といえる。 底本には、2011年にサンデイ・プレス・ブックス社から発売された増補版を使用した。 |
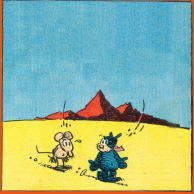 |
ジョージ・ヘリマン
|
| のんきもののクレイジー・キャットは鼠のイグナツが大好き。その求愛が我慢できないイグナツはことあるごとにクレイジーにレンガをぶつけるのだが、クレイジーの方はそれがイグナツが示す愛の証しと思い込んでいる。一方、犬のパップ巡査はイタズラなイグナツを監獄にぶちこもうと懸命なのだが、仕事熱心な顔の裏でひそかにクレイジーに心を寄せている。ココニーノ群の荒野を舞台にそんなおかしくも切ない三角関係が延々と繰り広げられる作品が『クレイジー・キャット』だ。 お話といえばほぼそれだけなのに、本作がコミックス史上の金字塔と讃えられているのにはわけがある。キャラクターの巧妙な造形、愛の不条理が生む悲喜劇、詩情溢れるセリフ回しといったものも、もちろん非凡というほかないのだが、大事なのはむしろそれらの要素を楽々と操りながら、同時に変幻自在なコマ割りや、キャラクターの後ろで不規則に変容し続ける背景といった実験に興じてみせる作者ジョージ・ヘリマンの精神の自由さ、ラディカルさの方だろう。 もともと『ディングバット・ファミリー』というマンガのオマケから発 |
展した本作は、連載中それほど一般的な人気を集めていたわけではなかったが、しだいにアンドレ・ブルトン、e・e・カミングズ、ウンベルト・エーコら、芸術家・知識人が賛辞を寄せるようになっていった。本作を愛した新聞社の社主ウィリアム・ハーストも、ヘリマンの死後、直ちに連載の終了を宣言する。誰にも彼の後を継ぐことができないのは明らかだったからだ。 今では本作がなければ、フィリックス・ザ・キャットもミッキー・マウスも、ひいてはのらくろも生まれなかっただろうといわれている。『コミックス・ジャーナル』誌が「20世紀のマンガ・ベスト100」の第1位に『クレイジー・キャット』を選出しているとおり(第2位は『ピーナッツ』)、作品の重要性とヘリマンの天才ぶりに対する評価は年を経るごとに高まっているといっていい。 本書には、白黒時代からカラー時代にかけての『クレイジー・キャット』(日曜版における最初の作品も掲載)のほか、貴重なヘリマンの初期作品を収録している。 |
 |
フランク・キング
|
| ある朝、家の前に赤ん坊が捨てられていたことから、ひとりものだったウォルト・ウォレットの人生は一変してしまった。ウォルトは男の子をスキージクスと名づけ、自分の手で育てることを決めるが、そのときからなんとウォルトとスキージクスは読者と同じスピードで成長を始めたのだった……。 マンガのキャラクターがリアルタイムで成長し続けるという試みを初めて行ったのが、本作『ガソリン・アレー』である。スキージクスは少年時代を過ぎると第二次大戦に従軍し、結婚し、さらには中年の危機を迎えることになるが、驚くべきことにはこの作品、作者フランク・キングの死後も、作者を替えてなお継続中なのだ(ウォルトに至っては110歳を超えて、いまだ存命!)。 キャラクターが読者とともに成長し続けるというコンセプトは、80年代から2000年代にかけてのアメリカの国民的コミック・ストリップ、リ |
ン・ジョンストンの『良かれ悪かれ For Better or For Worse』(1979-2008)などにも継承されているが、キャラクターが歳をとらないのが常識の日本の新聞マンガではまず考えられないことだろう。 子供を作品に登場させるのは、女性ファンをとりこもうとした編集者のアイディアだったが、その思惑は当たり、『ガソリン・アレー』は大ヒット作になった。美術学校を出たキングにとって、日曜版は平日版では不可能なアイディアを実験する絶好の舞台だったようで、はじめのころは自然や町の生活をいきいきと描写する程度だったが、1925年以降はさまざまな実験を行うようになり、表現主義的・モダニズム的な絵柄を作品に取り入れたり、一枚の絵を12コマに分割した中でストーリーを進めるといったなどの試みを果敢に行っている。 本書は、日曜版『ガソリン・アレー』初期のベスト・セレクションである。 |
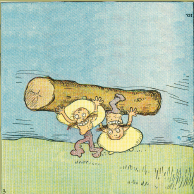 |
グスタフ・ヴァービーク
|
| 一見すると、少女とおじいさんが登場する6コママンガ。だけど、おや? 最後のコマで話が途中が終わっている。次回に続くのかなと思いきや、さにあらず。続きを読むには、ページを上下さかさまにするのである。すると、さっきまで読んでいた6コママンガが作品の後半に早変わり。さっきまでの少女はおじいさんに、おじいさんは少女に姿を変え、おじいさんが乗ったボートと魚と島は、少女をくわえている巨大な鳥になってしまうのだ。 こんな奇想天外な作品は、世界マンガ史にもほかに例を見ないだろう。この『ラヴキンズちゃんとマファルーじいさんのさかさま物語』を描いたのは、長崎生まれのマンガ家、グスタフ・ヴァービークである。父親のグイド・フルベッキ(Guido Verbeck。グスタフは渡米時に綴りをVerbeekに変更)はオランダ人宣教師で、大隅重信や副島種臣とも親交のある人物だった。グスタフは幼少期を日本で過ごしており、その経験が後の創作に大きな影響を与えているが、日本で得たヒントのひとつ |
に、笑っている顔を描いたものをひっくり返すと怒っている顔になる「上下絵(さかさ絵)」があったようだ。さかさまにすると違う絵になるだまし絵はヨーロッパにも古くから見られるものだが、洋の東西を問わずこうした発想があるというのは確かに興味深い。 本書には、1903年から05年にかけて発表された『さかさま物語』全64回分と、『ルルのあれれ?なリリック』全作、『ちっちゃなチビたちの珍道中』の一部を掲載した。詩が大好きな女の子ルルと、怪物を捕らえようとするお父さんの冒険を描いた『ルル』は、エドワード・リアやルイス・キャロルといった、ヴィクトリア朝のノンセンス詩と挿絵の伝統を汲む作品だ。『珍道中』では、4人の少年たちの前に、ゾウモリ傘、フラミンゴリラ、リゾットセイなど、かばん語(混成語)を駆使して生み出された動物たちが次々と登場する。しかし、時代は変わり、マンガに求められるものはノンセンスやスラップスティックからしだいに生活やリアリズムへ、さらには冒険や活劇へと変化していくのだった。 |